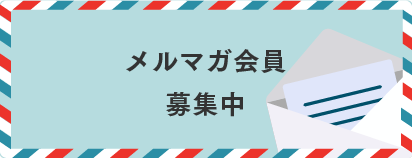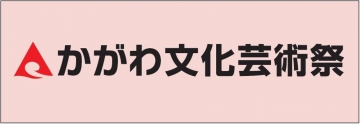木造船から五色台の絶景まで!【瀬戸内海歴史民俗資料館】で瀬戸内の暮らしを学ぶ!

瀬戸内海文化の資料収集、保管、研究を目的として1973年に開館した「瀬戸内海歴史民俗資料館(愛称:れきみん)」。瀬戸内地方の11府県という広域の民俗文化を対象とした全国的にも珍しい人文系博物館です。瀬戸内地域の充実した展示はもちろんのこと、フォトジェニックな建物や五色台の景観も大きな魅力。今回は館長の松岡明子さんに、歩くほどに瀬戸内がぐっと身近に感じられる「れきみん」をガイドしていただきました!


五色台の自然と融合した、独創的な建築
資料館は瀬戸内海国立公園内の五色台丘陵にあります。到着するとまず目に入るのは重厚感のある石積みの外観。「日本建築学会賞(作品賞)」や「第一回公共建築賞優秀賞」を受賞し、「公共建築百選」や「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」にも選出されるなど、建築物としても高い評価を獲得している建物です。この建物を見るために遠方から訪れる人も多く、中には海外から来る人もいるそうです。

「れきみん」の展示室は中庭を中心にぐるりと配置され、来館者は階段や屋外を通りながら館内を巡ります。エントランスにある模型を見るとその特徴がよく分かりますね。松岡さんによると、建物は自然公園である五色台に溶け込むように、最大約7mの高低差がある山肌に沿って建てられているそうです。大きな窓ガラスからは建設当時の植生がそのまま残されている庭を望むことができます。


石積みの外観も特徴的ですが、内観もフォトジェニック。第1展示室の天井は木造の枠が格子状になっており、照明部分が柔らかな光を放っています。「れきみん」を設計したのは当時、香川県土木部建築課長だった山本忠司(やまもと・ただし)氏。香川県庁舎計画をはじめ、数多くの公共建築を手がけた山本氏だからこそ、五色台の風土や地域の自然を生かした建築ができたのかもしれません。

迫力満点の木造船!瀬戸内に関する幅広い展示資料
館内の展示資料の数は約1,000点。所蔵する民俗資料約3万点のうちの約6,000点が国の重要有形民俗文化財に指定されています。一番広い第1展示室では瀬戸内各所から集めた渡し船や櫂伝馬船(かいでんません)、鯛網船などの木造船をはじめ、瀬戸内の暮らしを知るには欠かすことのできない海に関係した展示資料を見ることができます。木造船がずらっと並んでいる様子は圧巻の一言。内観のスタイリッシュなデザインと相まってとてもカッコイイですね。

船の他に、鯛網漁に用いる道具や海女用具、魚の標本などの展示も。潜水の時に胸の前に垂らす錘(おもり)である男木島の「ナマリ」は、かわいいキャラクターの顔のように見えませんか?網を編むためのアミバリ、棕櫚(しゅろ)の葉と稲わらで編んだ前掛けなど、一つひとつ手作業で丁寧に作られた用具たちは芸術作品のようにも感じられます。


入口付近には瀬戸大橋計画の際に採取されたボーリングコアが展示されています。実は、「れきみん」が建てられた場所は、本州と四国の間で海域が最も狭くなっているエリアで、瀬戸大橋がここに架かる可能性もあったそうです。地質調査の結果、現在橋が架かっている坂出に造られることになりましたが、そういった背景を知ると瀬戸内をより深く理解することに繋がりますね。

第1展示室の中2階では以前は民具等を展示していましたが、2021年から外部の団体や個人と連携した展示やセミナーなどを開催する瀬戸内ギャラリーに生まれ変わりました。瀬戸内地域の建築や昆虫をテーマにした展示や、東京芸術大学と連携した展示など、幅広い企画展が実施されています。「皆さんの活動から見た瀬戸内を発信してくださり、私たちも視野が広がりました」と松岡さんが言うように、従来とは異なる角度から瀬戸内を発信するギャラリーは「れきみん」の新たな魅力の一つになっています。

第2展示室には木造船の製作現場が再現され、工程の一部が分かりやすく展示されています。昔の船は部品一つひとつの寸法が載っているような詳細な設計図はなく、板図(いたず)と呼ばれる側面図を基に船大工が建造していたそうです。側面の絵から頭の中で図面を書き起こし、全て手作業でやっていたと思うと、昔の職人の技術の高さに驚きますね。


展示資料から見える時代や暮らしの変遷
展示品は日用品だけではなく、冠婚葬祭で使用する品々も並んでいます。「各地で行われていた祭礼や行事などがコロナ禍で中断し、少子高齢化などによりそのまま復活できていない地域もあります」と松岡さん。祭りや行事は口伝えで伝承され、紙の資料がないものも多くあります。地域の担い手や職人がいなくなり、現物も無くなると後世に復活させようにも手がかりが失われてしまうため、「れきみん」では無形民俗文化財に関する資料の収集にも力を入れているそうです。

そのほか、取材時にちょうど開催されていたテーマ展会場では、懐かしいコンピューターゲームや電話機を発見。さらに個人が所有していた土鈴などの旅行のお土産、新聞広告、家族アルバムの写真なども展示されていました。れきみんは、それぞれの時代、地域でどのような人がどんな暮らしをしていたのかを調査、研究することも目的の一つ。ここ数十年のうちに開発された電子機器も生活の変遷を物語る立派な民俗資料と言えます。展示を見ながら親子で「この時はこうだった」と話すのも楽しいかもしれませんね。

資料館の常設展示室は全部で8室に分かれています。展示資料も多岐にわたっているため、じっくり観賞するには1日は欲しいところ。「たくさんの資料をすべて見ようとすると疲れてしまうかもしれないので、興味のある展示を見るだけでもいいと思います。歴史や民俗の資料というと、少し難しく捉えられがちですが、例えば、“ナマリって顔みたい!”という見方でもOK。色々なテーマで展示しているので、興味を持ったものを入口にして自由に見ていただけたらと思います」と松岡さんは話してくれました。
瀬戸内海の大パノラマ!2024年は夜間開館も実施予定
さて、展示室を全部回ったから終わり……ではありません!「れきみん」に来たら見逃せないのが展望台からの景色。展望台へは展示室横にある空に向かって伸びたコンクリートの階段を上がります。展望台に上がるとそこは360度の絶景の世界!!青い瀬戸内海、男木島や女木島などの島々、五色台の豊かな自然が広がります。体の向きを変えれば見える景色が変わるのも山上にある展望台ならでは。春には南側に一面の桜が咲き誇るのが見えるそうです。

2024年は瀬戸内海国立公園指定90周年ということもあり、「れきみん」では夜間開館などのイベントも予定されています。「昼間の青い瀬戸内海と島々の景色も美しいですが、夜の暗闇に対岸の灯りが光っている様子も情緒たっぷり。夜間ならではの特別な景色を楽しんでほしいです」と松岡さん。

五色台の山上という立地、自然を生かしたユニークな建物、瀬戸内を多方面から知ることができる展示、新しい発見や体験をもたらすギャラリーやイベント……。見どころが数多くある博物館なのに入館料は無料というのも嬉しいですよね。さまざまな魅力がたっぷりと詰まったれきみん、瀬戸内海歴史民俗資料館で、瀬戸内を五感で体験してはいかがでしょう。

【瀬戸内海歴史民俗資料館】瀬戸内ギャラリー第12回企画展 伝統と創造 讃岐のり染 ―暮らしを彩る―